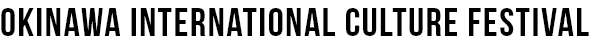お知らせ
【レポート】沖縄の社会課題解決を専門家と探る「ソーシャルビジネス・フォーラム」開催
2025.04.10

沖縄から新たなエンターテインメント文化を創造し、世界へ発信する『沖縄国際文化祭』では、貧困、教育、環境などさまざまな社会課題をビジネスで解決することを目的にするソーシャルビジネスのシンポジウム「ソーシャルビジネス・フォーラム」が4月6日、那覇市文化芸術劇場なはーと 小スタジオで開催されました。
登壇者は、ソーシャルビジネスの第一線で活躍する、岡田昌治さん(ユヌス・ジャパン代表理事/元九州大学教授)、阿座上陽平さん(ゼブラアンドカンパニー 代表取締役)、矢藤有希さん(ソニー知的財産サービス株式会社 シニアイノベーションマネジャー)の専門家3名です。
フォーラム前半は、ソーシャルビジネスの基本から、沖縄の地域課題に対してどのように取り組むべきかなどの講演を、3名がそれぞれ行いました。
ソーシャルビジネスの普及・啓発に取り組む岡田さんは、その概念や言葉の成り立ちから説明。さらに、日本人が江戸時代からやっている共感と感情が伴う生業こそソーシャルビジネスとして、7つの原則を解説しました。
リサーチに基づくビジョンミッション策定から企業を表す言葉やデザインのコンセプト作りを得意とする阿座上さんは、自信が推進するゼブラ企業について解説。それは、社会性と経済性がひとつになり、ソーシャルビジネスとほぼ同じとし、ゼブラ企業の哲学を説明したほか、ソーシャルビジネスの立ち上げ方から、具体的な運営方法まで取り上げました。
ソニーが取り組む環境素材「トリポーラス™」のプロジェクトマネージャーの矢藤さんは、米の籾殻が作った活性炭の多孔質カーボン素材のトリポーラス™の機能性と有用性を解説し、消臭剤や衣服など具体的な活用事例を紹介。循環型社会の形成に貢献する素材とアピールしました。
後半のパネルディスカッションでは、3つのテーマ「ソーシャルビジネスの始め方、関わり方」「地域で連携を生み出すための支援とは」「沖縄発ソーシャルビジネスの可能性と来年の展望」への議論が深められました。
阿座上さんは「ソーシャルビジネスをはじめるときには、解決したい課題があるはず。対象を見定め、課題の理由を調べて必要なアクションを起こす。効果が出るようになってから、事業化していけばいい」とはじめ方を指南しました。
また、沖縄発のソーシャルビジネスの可能性について、阿座上さんは「土壌や農業に関わる技術などをベースにしたソーシャルビジネスを作って、それが産業になる過程でほかの課題を解決するようになれば素晴らしい」と具体的な例を挙げます。矢藤さんは「いまPFAS(人工的に作られたフッ素が多い化合物の総称)は、沖縄だけでなく、世界各地で問題になっています。それを沖縄で解決していけば、世界へ発信されます」。トリポーラス™の活用がそのひとつの対策になることを説明しながら、「身近にある小さなことの積み重ねが大事です」と語りかけた。
岡田さんは最後に、いまソーシャルビジネスには追い風が吹いているとまとめました。「大学や企業の若い人たちの間では、社会貢献への意識が高い人が多く、行政もその波を感じて支援のための施策を打っています。身の回りにチャンスがある。どう実行したらいいか、周りの人と話してほしい。風を起こしてください」と呼びかけました。
そして「来年のこの会場でソーシャルビジネスのアイデアを発表するような場ができることを期待します」(岡田さん)と締めくくった。